Apple IntelligenceとCopilotの比較について、情報収集されているのではないでしょうか。
Copilot+ PCにおけるApple Intelligenceとの違いや、それぞれのAIで何ができるのか、結局のところ何がいい?のか、疑問は尽きませんよね。
この記事では、Apple Intelligenceは何に使えるのかという基本的な部分から、具体的な使い方や対応機種まで徹底解説します。
また、Apple IntelligenceとWindowsの連携は可能なのか、Apple IntelligenceとCopilotはどのように連携するのか、さらにはApple IntelligenceとChatGPTの比較はどうなのか、といった深い論点も掘り下げていきます。
あなたのAI選びの助けとなれば幸いです。
Apple IntelligenceとCopilotの比較|基本性能
- Apple Intelligenceは何に使えるのか
- それぞれのAIで何ができるのか
- Apple IntelligenceとCopilotの使い方
- Apple IntelligenceとCopilotの対応機種
- Apple IntelligenceとChatGPTの比較は?
Apple Intelligenceは何に使えるのか

Apple Intelligenceは、Apple製品の体験を根底から向上させるために設計された、パーソナルインテリジェンスシステムです。
単なる機能追加ではなく、iOS、iPadOS、macOSといったOS自体に深く統合されている点が最大の特徴と言えるでしょう。
これにより、ユーザー個人の文脈を深く理解し、日々のタスクをより直感的かつシームレスに支援します。
具体的には、以下のような場面でその能力を発揮します。
文章作成支援(Writing Tools)
メールやメモ、Pagesなどのアプリ内で、文章の校正、書き直し(リライト)、要約といった機能を利用できます。
例えば、友人宛のカジュアルな文章を、ビジネス向けのフォーマルなトーンに一瞬で書き換えることが可能です。
これにより、文章作成にかかる時間と労力を大幅に削減できます。
画像生成機能(Image Playground)
「アニメ」「イラスト」「スケッチ」といったスタイルで、簡単な指示から独自の画像を生成できます。
メッセージアプリ内で友人のオリジナル絵文字(Genmoji)を作成したり、メモに描いたラフスケッチから画像を生成したりと、創造的なコミュニケーションを豊かにしてくれます。
進化したSiri
Siriがより賢くなり、画面上の情報を認識して操作したり、アプリをまたいだ複雑な指示を理解したりできるようになります。
「昨日母から送られてきた写真を表示して」といった、より自然で曖昧な指示にも的確に応答可能です。
まさに、真のAIアシスタントへと進化を遂げます。
補足:パーソナルな文脈の理解
Apple Intelligenceの真髄は、あなたのカレンダー、メール、写真、人間関係といったプライベートな情報をデバイス内で安全に活用し、「あなただけの」応答を生成する点にあります。
このパーソナルな文脈理解こそが、他のAIとの大きな差別化ポイントです。
それぞれのAIで何ができるのか

Apple IntelligenceとCopilotは、文章の要約や画像生成など、一見すると似た機能を提供しています。
しかし、そのコンセプトと得意分野には明確な違いが存在します。
Appleが「個人の日常」に寄り添うことを目指す一方、Microsoftは「ビジネスの生産性向上」に重点を置いています。
ここでは、両者の代表的な機能を比較してみましょう。
| 機能 | Apple Intelligence | Copilot (in Windows) |
|---|---|---|
| コンセプト | OS統合型のパーソナルAI | WindowsやOfficeに特化した業務支援AI |
| 画像生成 | Image Playground:手軽で楽しい表現 | コクリエイター:ラフ画から本格的な画像を生成 |
| 画像編集 | 写真アプリ「クリーンアップ」:自然なオブジェクト削除 | ペイントアプリ「Cocreator」:よりクリエイティブな編集 |
| Web要約 | Safari:リーダー機能内で簡潔に要約 | Edge:Copilotサイドバーで詳細な箇条書き要約 |
| 文字起こし | ボイスメモ:高精度な自動文字起こしと要約 | ライブキャプション:リアルタイムの字幕表示 |
| PC操作支援 | 進化したSiriがアプリ横断で操作 | 設定変更やファイル検索などを指示可能 |
このように、例えば画像のオブジェクト削除機能一つをとっても、Apple Intelligenceはより自然な補完を重視する傾向があり、Copilotはクリエイティブな側面を強調するなど、アプローチが異なります。
どちらが良いということではなく、それぞれの思想が機能に反映されていると理解することが重要です。
Apple IntelligenceとCopilotの使い方

両者のAI機能は、それぞれのOSに深く根差した形で提供されるため、使い方にも違いが見られます。
特別なアプリを起動するのではなく、日常的に使うツールの中で自然にAIのサポートを受けられる点が共通しています。
Apple Intelligenceの使い方
Apple Intelligenceは、OSのあらゆる場面で呼び出すことができます。
例えば、
- メール作成時:ツールアイコンをタップして「下書きを校正」「トーンを変更」などを選択します。
- SafariでWeb閲覧中:リーダー表示アイコンから「要約する」を選択します。
- Siri:従来通り音声で呼び出すか、テキストで指示を入力することも可能です。
基本的に、ユーザーが「AIを使っている」と意識することなく、必要な時にサッと機能を引き出せる直感的なUIが特徴です。
Copilotの使い方
WindowsにおけるCopilotは、主に2つの方法で利用します。
- Copilot in Windows:タスクバーのCopilotアイコン、または「Win + C」キーで専用のサイドバーを呼び出し、対話形式でPCの設定変更やWeb検索などを指示します。
- Microsoft 365アプリ内:WordやExcel、PowerPointのリボンに表示されるCopilotアイコンから、文書の生成や要約、データ分析、スライド作成などを実行します。
ポイント:統合レベルの違い
Apple IntelligenceはOS全体に溶け込む「環境型」のAIであるのに対し、Copilotは特定のアプリやサイドバーという「呼び出し型」の側面が強いと言えます。
この使い勝手の違いが、ユーザーの作業フローに影響を与える可能性があります。
Apple IntelligenceとCopilotの対応機種
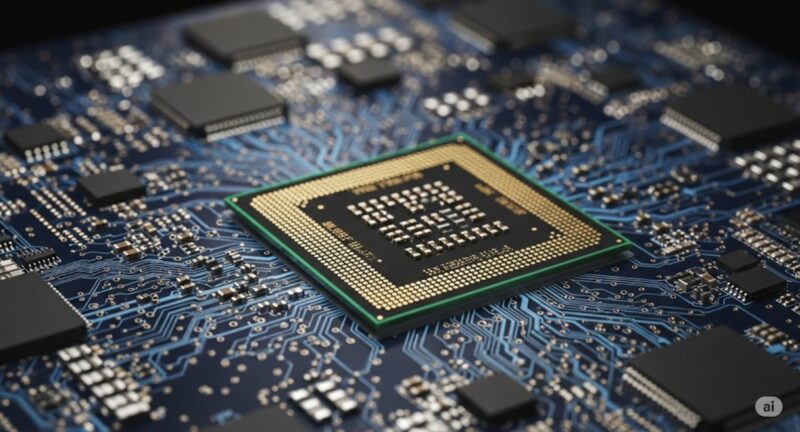
これらの先進的なAI機能を利用するには、残念ながら誰でも使えるわけではなく、強力なNPU(Neural Processing Unit)を搭載した比較的新しいデバイスが必要です。
オンデバイスでの高速なAI処理を実現するため、一定のハードウェア要件が設定されています。
Apple Intelligenceの対応機種
Apple Intelligenceを利用できるのは、以下のAppleシリコンを搭載したモデルに限られます。
- iPhone:A17 Proチップ以降を搭載したモデル (iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max 以降)
- iPad:M1チップ以降を搭載したモデル (iPad Pro, iPad Air)
- Mac:M1チップ以降を搭載したモデル (MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac miniなど)
注意:iPhone 15の無印モデルは非対応
同じiPhone 15シリーズでも、標準モデルとPlusモデルに搭載されているA16 Bionicチップでは、Apple Intelligenceを利用できません。
デバイス購入の際は、この点を十分に確認する必要があります。
Copilotの対応機種(Copilot+ PC)
Microsoftの定義するAI PC「Copilot+ PC」は、以下の要件を満たす必要があります。
- NPU性能:40TOPS以上(1秒間に40兆回のAI演算が可能)の性能を持つNPU
- メモリ:16GB以上
- ストレージ:256GB以上のSSD
現在、この要件を満たす主なCPUはQualcommの「Snapdragon X Elite」および「Snapdragon X Plus」です。
今後は、Intelの「Lunar Lake」やAMDの「Ryzen AI 300」シリーズを搭載したモデルも登場予定で、選択肢は広がっていく見込みです。
Apple IntelligenceとChatGPTの比較は?

Apple Intelligenceは、特定の高度なリクエストに応えるため、外部のAIモデルと連携する機能を備えています。
その最初のパートナーが、OpenAIのChatGPT(GPT-4o)です。
では、この連携はどのような位置づけなのでしょうか。
OSに統合されたシームレスな連携
Siriや文章作成ツール内で、より専門的な知識や創造性が必要だと判断された場合、Apple Intelligenceはユーザーの許可を得た上でChatGPTに処理を依頼します。
このとき、別途アプリを起動したり、アカウントにログインしたりする必要はありません。
OSの機能の一部として、シームレスにChatGPTの能力を活用できます。
例えば、「5歳の子供向けの、宇宙をテーマにしたおやすみ前の物語を考えて」といったクリエイティブな要求に対して、Siriが「ChatGPTに手伝ってもらっても良いですか?」と尋ね、許可すると物語を生成してくれる、といった連携が想定されます。
プライバシーへの配慮
この連携において、Appleはプライバシー保護を最優先に考えています。ChatGPTに送信されるリクエストはIPアドレスなどが秘匿され、OpenAIがリクエストを保存することはありません。
ユーザーのプライバシーは、Appleの基準で保護されます。
Apple IntelligenceとChatGPTの役割分担
両者の関係は、以下のように整理できます。
- Apple Intelligence:デバイス上の個人情報を活用し、「あなたのこと」を深く理解するパーソナルAI。
- ChatGPT:広範な世界の知識を持ち、専門的な質問や創造的なタスクをこなす汎用AI。
つまり、Apple Intelligenceが日常のタスクをこなし、手に負えない部分を専門家であるChatGPTに相談する、という補完関係にあるのです。
これは、CopilotがBing検索と連携して最新情報を提供する関係性と似ていますが、OSレベルでの統合度とプライバシー設計において、Appleのアプローチは一線を画しています。
Apple IntelligenceとCopilotの比較|選び方のポイント
- Apple IntelligenceとWindowsの連携
- Copilot+ PCとApple Intelligenceの違い
- Apple IntelligenceとCopilotの連携
- 結局どちらのAIが何がいいのか
- Apple IntelligenceとCopilotの比較まとめ
Apple IntelligenceとWindowsの連携

Apple Intelligenceの機能をWindows PC上で直接的に利用することは、現時点の技術的、戦略的な背景から見て不可能と考えられます。
これは単に企業の方針というだけでなく、Apple Intelligenceが機能するための根本的な仕組みに理由が存在します。
Apple Intelligenceは、Appleが自社で設計する「Apple Silicon」(MシリーズやAシリーズのチップ)に搭載されたNeural EngineというAI処理専門のハードウェア上で動作することを前提に構築されています。
このため、OSレベルでAI機能がチップと深く結びついており、異なるハードウェア構成を持つ一般的なWindows PCでは、この中核機能を動かすことができません。
注意:エコシステムという技術的な壁
Appleの強みは、ハードウェアからソフトウェア、そしてAIモデルまでを一貫して自社で開発・最適化している点にあります。
Apple Intelligenceは、この閉じたエコシステムの中で最高の性能とプライバシーを発揮するように設計されているのです。
Windowsのような外部のプラットフォームにこの機能を提供することは、Appleが築き上げてきたこの優位性を自ら手放すことになり、戦略的に考えにくいでしょう。
データの同期とAI処理は全くの別物
しかし、「連携」という言葉をもう少し広く捉えることは可能です。
例えば、Microsoftが提供する「iCloud for Windows」というアプリを使えば、Windows PC上でもiCloudに保存された写真やファイル、カレンダーの予定などを閲覧・編集できます。
ただ、これはあくまでクラウドを介した「データの同期」に過ぎません。
Windows PC上であなたの写真データをAIが解析し、「去年の夏に海で撮った、犬が写っている写真を探して」といった文脈を理解した操作を実行することは不可能です。
そのような「知能」にあたる部分は、Neural Engineを搭載したiPhoneやMac側でしか処理されないからです。
補足:間接的な連携の具体例
Apple MusicやApple TV+といったコンテンツ配信サービスは、Windows向けのアプリが提供されています。
これらはコンテンツを再生するためのプラットフォームであり、OSに統合されたAI機能とは性質が異なります。
このように、サービス単位での連携と、OSの中核をなすAI機能の連携は、明確に区別して考える必要があります。
今後の展望を考えても、Apple IntelligenceがOSの機能としてWindowsに対応する可能性は極めて低いと見るのが妥当です。
むしろ、AI技術が進化する中で、将来的にはブラウザ上で動作する高機能なWebサービス型のAIが登場し、OSの垣根を越えて利用できる場面が増えていくかもしれません。
そのような形での「連携」が、より現実的な未来像と言えるでしょう。
Copilot+ PCとApple Intelligenceの違い

前述の通り、Copilot+ PCとApple Intelligence(を搭載したMac)は、どちらもオンデバイスAIを主軸に据えた次世代のコンピュータですが、その根底にある思想とアーキテクチャは大きく異なります。
この違いを理解することが、どちらを選ぶかの重要な判断基準となります。
処理の思想:オンデバイス vs ハイブリッド
両者の最大の違いは、AI処理に対する考え方です。
- Copilot+ PC:Microsoftは「Recall(リコール)」機能のように、ユーザーのPC操作のほぼ全てをローカルに記録・分析する、徹底したオンデバイスAIを志向しています。これは、ユーザーデータを外部に出さないというプライバシー上のメリットと、強力なパーソナライズを実現する可能性を秘めています。
- Apple Intelligence:Appleは、オンデバイス処理を基本としつつ、より複雑な処理が必要な場合は「Private Cloud Compute(PCC)」という独自のクラウドに処理を委ねるハイブリッドアプローチを採用しています。
Private Cloud Compute(PCC)とは?
PCCは、Appleシリコンを搭載した専用サーバーで構成される、プライバシーを最優先に設計されたクラウドです。
デバイスから送られるデータは暗号化され、サーバー上に保存されることはなく、Apple自身もアクセスできません。
さらに、この仕組みは独立した専門家による検証が可能となっており、透明性も確保されています。
アーキテクチャの違いがもたらすもの
この違いにより、Copilot+ PCはより強力なNPU性能をPC自体に要求する一方、Appleはデバイスの性能を超える高度なAI処理を、プライバシーを犠牲にすることなく提供できるというメリットがあります。
MicrosoftがPCの性能に賭けるのに対し、Appleはエコシステム全体の連携で勝負するという戦略の違いが見て取れます。
Apple IntelligenceとWindowsの連携
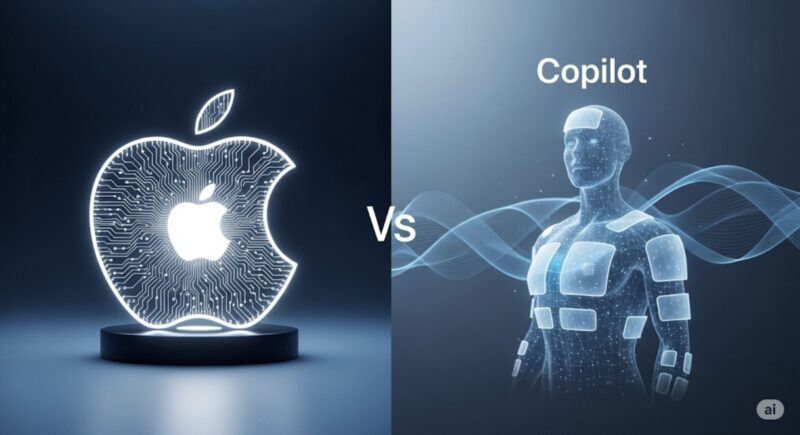
Apple Intelligenceの機能をWindows PC上で直接的に利用することは、現時点の技術的、戦略的な背景から見て不可能と考えられます。
これは単に企業の方針というだけでなく、Apple Intelligenceが機能するための根本的な仕組みに理由が存在します。
Apple Intelligenceは、Appleが自社で設計する「Apple Silicon」(MシリーズやAシリーズのチップ)に搭載されたNeural EngineというAI処理専門のハードウェア上で動作することを前提に構築されています。
このため、OSレベルでAI機能がチップと深く結びついており、異なるハードウェア構成を持つ一般的なWindows PCでは、この中核機能を動かすことができません。
注意:エコシステムという技術的な壁
Appleの強みは、ハードウェアからソフトウェア、そしてAIモデルまでを一貫して自社で開発・最適化している点にあります。
Apple Intelligenceは、この閉じたエコシステムの中で最高の性能とプライバシーを発揮するように設計されているのです。
Windowsのような外部のプラットフォームにこの機能を提供することは、Appleが築き上げてきたこの優位性を自ら手放すことになり、戦略的に考えにくいでしょう。
データの同期とAI処理は全くの別物
しかし、「連携」という言葉をもう少し広く捉えることは可能です。
例えば、Microsoftが提供する「iCloud for Windows」というアプリを使えば、Windows PC上でもiCloudに保存された写真やファイル、カレンダーの予定などを閲覧・編集できます。
ただ、これはあくまでクラウドを介した「データの同期」に過ぎません。Windows PC上であなたの写真データをAIが解析し、「去年の夏に海で撮った、犬が写っている写真を探して」といった文脈を理解した操作を実行することは不可能です。
そのような「知能」にあたる部分は、Neural Engineを搭載したiPhoneやMac側でしか処理されないからです。
補足:間接的な連携の具体例
Apple MusicやApple TV+といったコンテンツ配信サービスは、Windows向けのアプリが提供されています。
これらはコンテンツを再生するためのプラットフォームであり、OSに統合されたAI機能とは性質が異なります。
このように、サービス単位での連携と、OSの中核をなすAI機能の連携は、明確に区別して考える必要があります。
今後の展望を考えても、Apple IntelligenceがOSの機能としてWindowsに対応する可能性は極めて低いと見るのが妥当です。
むしろ、AI技術が進化する中で、将来的にはブラウザ上で動作する高機能なWebサービス型のAIが登場し、OSの垣根を越えて利用できる場面が増えていくかもしれません。
そのような形での「連携」が、より現実的な未来像と言えるでしょう。
結局どちらのAIが何がいいのか

これまで比較してきた内容を踏まえ、どちらのAIがどのようなユーザーに向いているのか、その選択基準を整理します。
これは優劣の問題ではなく、あなたの使い方や価値観にどちらが合っているかという視点が重要です。
Apple Intelligenceがおすすめな人
- Apple製品を複数利用している:iPhone, iPad, Macを日常的に使い、デバイス間のシームレスな連携を重視する人。
- プライバシーを最優先に考える:個人データが外部に送信されることに強い懸念を持つ人。AppleのPCCを含むプライバシー設計は大きな安心材料となります。
- 直感的で簡単な操作を好む:AIを意識せず、OSに溶け込んだ自然な形でサポートを受けたい人。
Copilot (Copilot+ PC)がおすすめな人
- Windows PCとMicrosoft 365が仕事の中心:Word, Excel, Teamsなどを多用し、業務の生産性を最大限に高めたいビジネスパーソン。
- オープンな環境を好む:様々なメーカーから発売される多様なPCから、自分の好きなデザインや性能のモデルを選びたい人。
- AIの機能を積極的にカスタマイズしたい:より詳細な指示や設定で、AIを自分のアシスタントとして能動的に活用したい人。
最終的な判断軸
もしあなたが「生活」全体を豊かにするパートナーを求めているならApple Intelligenceが、「仕事」の効率を極限まで高めるツールを探しているならCopilotが、現時点での最適な選択肢となる可能性が高いでしょう。



