Redmiシリーズは手頃な価格と高性能で多くのユーザーに愛されていますが、さらに快適な使い心地や最新機能を求めるユーザーの間ではRedmiのCustom (カスタム) ROMの導入が注目されています。
本記事では、Redmi 12 5gやRedmi Turbo 3、Redmi note 10 je、Xiaomi 14、Poco F6といった人気モデルを中心に、カスタムROMの基本からROM焼きの方法までを詳しく解説します。
カスタムROMの導入は自由度を大きく広げる一方で、作業には注意点やリスクも伴います。
自分で導入するのが不安な方には代行サービスの選択肢もあります。
これからRedmiのCustom (カスタム) ROMに挑戦しようと考えている方に向けて、安全にかつ確実に導入するための情報をわかりやすくまとめました。
まずはカスタムROMの基礎知識からしっかり理解していきましょう。
初心者向けRedmiのCustom (カスタム) ROMガイド
- RedmiのCustom (カスタム) ROMとは?基本知識と魅力
- Xiaomi機種とRedmiのCustom (カスタム) ROMの関係
- Redmi Turbo 3 ROM焼きの手順と注意点
- Redmi 12 5G カスタムROM導入のポイント
- Redmi Note 10 JE カスタムROMの対応状況
- Xiaomi 14 ROM焼きの特徴と手順
RedmiのCustom (カスタム) ROMとは?基本知識と魅力

RedmiのCustom ROMとは、Redmiスマートフォンに搭載されている標準のMIUIやHyperOSの代わりに、ユーザーが独自に開発されたAndroidベースのオペレーティングシステムをインストールすることを指します。
このカスタムROMには公式版にはない機能やカスタマイズ性が提供されているため、多くの愛好者や開発者に支持されています。
まず、カスタムROMの最大の魅力は、ユーザーの自由度が大きく広がる点です。
例えば、メーカーのアップデートが止まってしまった古い機種でも、最新のAndroidバージョンにアップデートできる場合があります。
これにより、使い慣れた端末をより長く快適に使い続けることができます。
また、標準ROMでは制限されている細かい設定やUIの変更、プリインストールアプリの削除なども可能になります。
次に、動作の軽快さが挙げられます。
カスタムROMの多くは不要な機能やアプリが削ぎ落とされており、シンプルで動作がスムーズです。
これによって、特にエントリークラスやミドルクラスのRedmi端末でもパフォーマンスの改善が期待できます。
一方で、デメリットも存在します。
まず、カスタムROMの導入にはブートローダーのアンロックやリカバリーの書き換えといった技術的な知識が求められます。
加えて、導入したROMによっては一部の機能が正しく動作しない場合や、不安定になることもあります。
最悪の場合、端末が起動しなくなるリスクもあるため、事前の調査とバックアップは必須です。
このように考えると、RedmiのカスタムROMは、使い勝手を追求したいユーザーや開発者には非常に魅力的な選択肢ですが、慎重な準備と知識が必要な作業でもあります。
まずは対応機種や導入方法について情報収集を徹底することをおすすめします。
Xiaomi機種とRedmiのCustom (カスタム) ROMの関係
RedmiはXiaomiのサブブランドとして多くのスマートフォンを展開しています。
そのため、Xiaomi機種とRedmi機種には共通する設計やソフトウェア構成が多く、カスタムROMにおいても非常に密接な関係があります。
一般的に、XiaomiやRedmiの端末はブートローダーアンロックが公式に認められているため、カスタムROMの導入が比較的容易な部類に入ります。
特に、Redmiシリーズはグローバル市場向けに広く販売されており、開発者コミュニティも活発です。
これにより、Redmi機種専用やXiaomi機種と共通のカスタムROMが多数存在します。
例えば、Redmi Note 11(コードネーム:spes)やRedmi Note 10 Pro(sweet)はXiaomi製スマートフォンと同様に多くのカスタムROMに対応しています。
このことがRedmiユーザーの間でカスタムROMの人気を支えています。
しかし、Xiaomi機種とRedmi機種で注意が必要なのは、同じモデル名やスペックであっても、地域やキャリアによってハードウェア構成が異なるケースがあることです。
これにより、カスタムROMを導入してもFeliCaやNFC、VoLTEなどが正しく機能しないことがあります。
前述の通り、日本版では特にFelicaやeSIM対応の有無による差異が顕著です。
また、一部のRedmiキャリア版では初期ROMが非公開だったり、特殊なファームウェアが必要になるケースもあります。
このような場合は、同一シリーズのSIMフリーモデルのROMを利用することで、カスタムROMの導入やRoot化が可能になる場合もあります。
このように、XiaomiとRedmiのカスタムROM事情は密接に絡み合っていますが、導入にあたっては自身の機種やバージョンが対応しているか慎重に確認することが非常に重要です。
Redmi Turbo 3 ROM焼きの手順と注意点

Redmi Turbo 3はその高性能とコストパフォーマンスの良さから注目されているモデルですが、ROM焼き(カスタムROMの導入)も比較的盛んに行われています。
ここでは、Redmi Turbo 3へのROM焼きの基本手順と注意点をご紹介します。
まず最初に、ROM焼きにはブートローダーのアンロックが必須です。
Xiaomi公式サイトのMi Unlock Toolを使用し、事前にアカウント登録と端末の登録を行う必要があります。
通常、アンロック申請後には待機期間が設けられています。
次に、カスタムリカバリー(例:TWRP)をインストールします。
これにより、端末にカスタムROMやMagisk(Root化ツール)などをインストールできる環境が整います。
TWRPをインストールする際は、fastbootモードでPCと接続し、コマンドを用いて書き込みます。
その後、実際に導入したいカスタムROMを端末に転送し、TWRPからインストールします。
Redmi Turbo 3はRedmi K80(コードネーム:zorn)のリネームモデルとして知られており、これに対応したカスタムROMを選ぶことが重要です。
ROM選びを誤ると、端末が起動しない、いわゆる文鎮化状態になるリスクがあるため慎重な判断が求められます。
ここで注意すべき点は、MTK(MediaTek)やSnapdragonなど、チップセットによるカスタムROMの互換性です。
Redmi Turbo 3はSnapdragon搭載のため、比較的対応ROMは多いですが、それでも対応端末やバージョンを間違えると不具合が発生します。
また、導入後にVoLTEやFeliCaなど一部機能が正常動作しないこともあります。
最後に、万が一に備えて必ずフルバックアップを取ってから作業を行ってください。
これには、EFS領域やmodemパーティションなども含まれます。
復旧用の公式ROMも事前にダウンロードしておくと安心です。
このように、Redmi Turbo 3へのROM焼きは正しい手順を守れば実現可能ですが、細心の注意と十分な準備が不可欠です。
初めて挑戦する場合は、必ず信頼できる情報源やコミュニティのガイドを参照することを強く推奨します。
Redmi 12 5G カスタムROM導入のポイント
Redmi 12 5GはSnapdragon 4 Gen 2を搭載し、比較的パフォーマンスが安定しているため、カスタムROMの導入に向いているモデルとされています。
ただし、導入する際にはいくつかの重要なポイントに注意が必要です。
まず、この機種は日本版(コードネーム:sky)とグローバル版が存在します。
特に日本版はFeliCaやおサイフケータイ機能が搭載されており、グローバルROMや一部カスタムROMを導入した際に、これらの機能が動作しなくなることがあります。
Magiskモジュールなどを使うことで対応できる場合もありますが、100%の保証はありません。
導入を考える前に、自身の利用スタイルをよく考慮することが求められます。
次に、ブートローダーのアンロックが必要です。
Xiaomiは公式にブートローダーアンロックを認めており、Mi Unlock Toolを使ってアンロックできます。
しかし、申請から解除までに待機期間が発生するため、計画的に準備を進める必要があります。
また、カスタムROMを焼く前には必ず純正ROMやEFS、modem領域のバックアップを取ることが強く推奨されます。
万が一の不具合や起動不能状態(いわゆる文鎮化)に備えておくことで、元の状態に戻すことが可能になります。
カスタムROM選びについては、Redmi 12 5Gは比較的新しい機種のため、対応ROMの種類はやや限られています。
公式フォーラムやカスタムROM配布サイトで事前に確認することが大切です。
導入後のトラブル回避のためにも、同じモデル・バージョンで実績のあるROMを選ぶことをおすすめします。
このように、Redmi 12 5GはカスタムROM導入に適した機種ですが、日本版特有の仕様や機能制限には十分注意し、事前の情報収集とバックアップが成功の鍵となります。
Redmi Note 10 JE カスタムROMの対応状況

Redmi Note 10 JE(型番:XIG02、コードネーム:iris)は、日本市場専用に設計された非常に特殊なモデルです。
そのため、他のRedmiシリーズと比較するとカスタムROMの選択肢は限られています。
この機種はau専売モデルで、海外版の同型機種やROMは存在しません。
これがカスタムROM導入の障壁となっています。
通常、カスタムROMはグローバル市場で販売されている機種を対象に開発されるため、Redmi Note 10 JE向けに最適化されたカスタムROMは非常に少数です。
しかし、希望が全くないわけではありません。
Redmi Note 10 JE用に非公式ながらTWRPが開発され、一部の開発者コミュニティではLineageOSベースのカスタムROMがテスト的に公開されています。
動作は基本的な部分では問題ないものの、FelicaやeSIM機能など、地域限定の独自機能は動作しないケースが多いです。
これには、前述の通り特別なハードウェアやファームウェアの違いが関係しています。
さらに、カスタムROMを焼くためにはブートローダーアンロックが必要です。
Xiaomi公式のMi Unlock Toolで対応は可能ですが、au端末特有の挙動や制約があるため、導入には慎重な判断が求められます。
このように、Redmi Note 10 JEはカスタムROMの選択肢が非常に少なく、導入には高度な知識とリスクへの理解が必須です。
手軽にカスタムROMを楽しみたい方には他のグローバルモデルの選択をおすすめします。
一方で、研究やチャレンジ目的であれば、貴重な経験が得られる端末とも言えるでしょう。
Xiaomi 14 ROM焼きの特徴と手順
Xiaomi 14シリーズは最新のフラッグシップ機として高性能を誇る一方で、カスタムROM愛好者にとっても非常に注目されています。
特に、Xiaomi 14 Ultra(コードネーム:aurora)などはグローバル市場と日本市場で同仕様となっているため、カスタムROMの導入も比較的スムーズに行える特徴があります。
まず、ROM焼きを行うにはブートローダーのアンロックが必要です。
Xiaomiは公式にMi Unlock Toolを提供しており、ユーザーはアカウント登録と端末登録を行い、数日から1週間程度の待機期間を経て解除できます。
この手続きはセキュリティ上のリスクを伴うため、事前にデータのバックアップが必須です。
次に、TWRPなどのカスタムリカバリーをインストールします。
これによりカスタムROMのフラッシュやMagiskなどのRoot化ツールが使用できるようになります。
導入したいカスタムROMを事前に確認し、端末に対応しているバージョンを正確に選ぶことが重要です。
Xiaomi 14向けにはLineageOSやPixel Experienceなどがすでに開発されているケースもあります。
ROM焼きの際には、事前に必ずフルバックアップを取っておくべきです。
これには、EFSやmodem領域などの重要なパーティションも含めることを推奨します。
失敗した場合でも、公式ROM(Fastboot ROM)を用いて元の状態に復旧することが可能です。
注意点として、Xiaomi 14では特にFelicaやおサイフケータイの互換性に問題が出る場合があります。
日本版特有のモジュールをMagisk経由で導入することで改善できる場合もありますが、必ずしも完全ではありません。
このように、Xiaomi 14は最新機種ながらROM焼きの自由度が高く、カスタムROMの導入が比較的進めやすいモデルです。
しかし、十分な準備と情報収集を行い、安全に作業を進めることが求められます。
最新情報で学ぶRedmiのCustom (カスタム) ROMの活用法
- カスタムROMの種類と選び方
- カスタムROMの導入前に必要な準備
- ROM焼き代行サービスの利用と注意点
- Xiaomi端末のブートローダーアンロック方法
- Poco F6 カスタムROM導入のメリットと注意
- Redmi端末にカスタムromを導入する際のリスク
カスタムROMの種類と選び方

カスタムROMは、標準のOSに対して独自のカスタマイズや機能を追加したAndroidベースのシステムです。
Redmiを含むXiaomi端末では多くのカスタムROMが提供されており、それぞれに特徴があります。
まず代表的なカテゴリとして、MIUIベースとAOSP(Android Open Source Project)ベースがあります。
MIUIベースの代表例はeuROMです。
これは中国版MIUIから不要なアプリを除去し、多言語対応やGoogleサービスを標準搭載したものです。
元のMIUIの使い勝手を保ちながら不要な要素を排除したい人に適しています。
ただし、FelicaやeSIMなど日本専用機能が無効になるケースもあります。
一方で、AOSP系ROMはGoogleの純正Androidに近いシンプルなUIと軽快な動作が特徴です。
代表的なものにLineageOS、Pixel Experience、crDroidなどがあります。
これらは標準MIUIに比べて動作が軽く、広告や不要アプリもありません。
Redmi Noteシリーズでは特に人気があります。
カスタムROMを選ぶ際のポイントは、自分の用途と機種の対応状況をよく確認することです。
例えば、性能向上や見た目のカスタマイズを重視するならAOSP系が適しています。
逆にMIUIの操作感を維持したい場合はeuROMのようなMIUIベースを選ぶと良いでしょう。
また、自分のRedmi端末のモデル名とコードネームが対応ROMに含まれているかを事前に確認することが非常に重要です。
さらに、開発が活発でサポートが続いているROMを選ぶことも失敗を防ぐコツです。
開発終了や更新停止となったROMでは、セキュリティパッチや不具合修正が行われなくなるため、長期使用には向きません。
このように、自身のニーズと端末の互換性、ROMの安定性を総合的に判断して選択することが、カスタムROMの導入成功への近道となります。
カスタムROMの導入前に必要な準備
カスタムROMを導入する前には、いくつかの重要な準備が必要です。
準備不足は端末の不具合や起動不能といった深刻なトラブルにつながるため、慎重に進めることが求められます。
まず最初に行うべきことは端末のブートローダーアンロックです。
Xiaomi端末の場合、Mi Unlock Toolを利用してアンロック申請を行い、数日から1週間程度待つ必要があります。
アンロックをしない限りカスタムリカバリーやカスタムROMの導入はできません。
次に、バックアップの取得が不可欠です。
データ、写真、アプリだけでなく、EFS領域やmodemファイルなどシステムに関わるパーティションもバックアップすることを強く推奨します。
こうすれば、万が一失敗しても元の状態に戻すことができます。
さらに、カスタムリカバリーの準備が必要です。
TWRP(Team Win Recovery Project)が最も広く使われています。
これを導入することで、ROMのインストールやシステムのバックアップが簡単に行えるようになります。
また、カスタムROMと一緒に導入するGApps(Google Apps)パッケージの準備も忘れずに行います。
AOSP系のROMにはGoogle PlayやGmailが含まれていないため、GAppsを別途用意する必要があります。
これを理解した上で、導入するROMの開発元サイトやフォーラムで提供されている手順書や注意事項を必ず確認してください。
特に機種固有の制約や必要なパッチが記載されている場合もあります。
最後に、PCや通信ケーブル、端末のバッテリー残量を十分に確保することも重要です。
途中で電源が落ちると致命的なエラーにつながることがあります。
このように、事前準備はカスタムROM導入の成功を左右します。
焦らずに計画的に準備を進めることが、安全かつスムーズな作業の鍵となります。
ROM焼き代行サービスの利用と注意点

近年、カスタムROMの人気の高まりに伴い、ROM焼きを代行するサービスが増えてきました。
これらは自分で導入作業を行うのが不安な方や、技術的な知識がない方にとっては魅力的な選択肢に映ります。
しかし利用には慎重さが必要です。
ROM焼き代行サービスの大きな利点は、作業の失敗リスクを減らせることです。
専門知識を持つスタッフが手順通りに作業するため、自分で行うよりも成功率が高くなります。
また、作業時間や手間を省けるため忙しい方にも便利です。
ただし、このようなサービスのリスクや注意点も理解しておく必要があります。
まず第一に、カスタムROMの導入はメーカー保証外行為であり、万が一端末に不具合が生じてもメーカーやキャリアのサポートを受けられなくなることがあります。
さらに、信頼性の低い業者を利用すると、個人情報の流出やデータ消失といった深刻な問題につながる危険もあります。
端末を預ける際には、内部データを必ず初期化し、SDカードやSIMカードは抜いておくことが最低限の対策です。
また、代行業者によっては対応機種やカスタムROMの種類が限られている場合があります。
事前に自分の機種と希望するROMが対応しているかを確認する必要があります。
料金についても業者によってばらつきが大きく、中には法外な費用を請求するところもあるため、複数業者の料金と実績を比較検討することが重要です。
いくら利便性が高くても、代行サービスの利用は自己責任で行う必要があります。
可能であれば、まずは自分自身でカスタムROMの仕組みや手順を理解し、信頼できる業者かどうかを見極める力を身につけておくことをおすすめします。
このように、ROM焼き代行サービスは便利な反面リスクも伴います。
利用を検討する際にはメリットとデメリットの両面をよく把握して判断することが大切です。
Xiaomi端末のブートローダーアンロック方法
Xiaomi端末でカスタムROMを導入するには、まずブートローダーのアンロックが必要です。
ブートローダーとは、端末の起動時にシステムの整合性をチェックするプログラムのことで、通常は不正なシステム改変を防ぐためにロックされています。
これを解除することで、カスタムリカバリーやカスタムROMの導入が可能になります。
まず、事前準備としてMiアカウントの作成が必要です。
Miアカウントにログインした状態で、開発者オプションから「OEMロック解除」を有効にし、「Mi Unlock Status」から端末をアカウントに紐づけます。
次に、PC側ではMi Unlock Toolを用意します。
公式サイトからダウンロードできるこのツールは、アンロック申請と解除を行うための専用ソフトです。
端末をfastbootモード(電源ボタン+音量下ボタン長押し)にしてPCに接続し、Mi Unlock Toolを起動します。
Mi Unlock Toolにログイン後、「Unlock」ボタンをクリックします。
しかしここで注意が必要です。
通常、すぐにアンロックはされず、最大で168時間(約7日間)の待機期間が設けられます。
この間、端末は通常通り使用できますが、再度fastbootモードで接続し、待機時間経過後に改めてアンロック作業を完了させる必要があります。
ブートローダーのアンロックにはメリットとデメリットがあります。
アンロックによりカスタムROMの導入やRoot化が可能になりますが、メーカー保証が無効になる点や、端末のセキュリティレベルが低下する点に留意する必要があります。
また、銀行系アプリや一部ゲームアプリが動作しなくなる場合もあります。
このように、Xiaomi端末のブートローダーアンロックは比較的わかりやすい手順で行えますが、しっかりと準備し、自己責任で実施することが大切です。
Poco F6 カスタムROM導入のメリットと注意
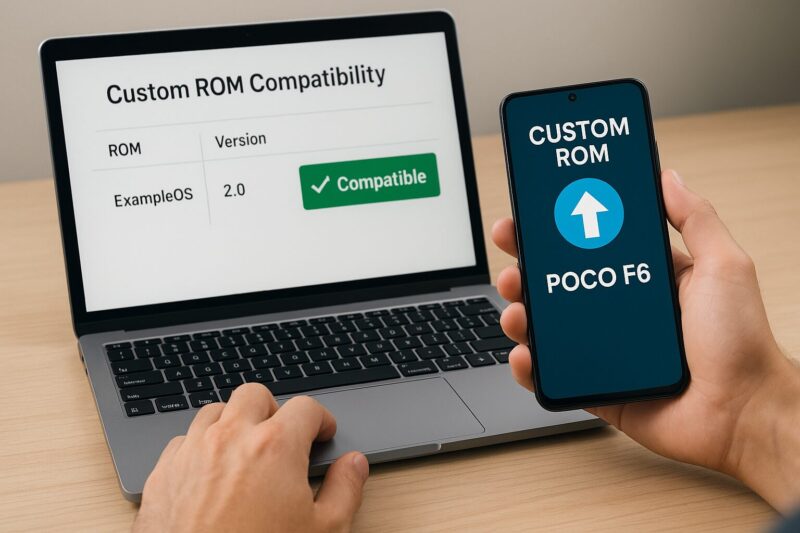
Poco F6は高性能なSnapdragon 8 Gen 2を搭載し、Redmi K70のリネームモデルとして登場しました。
これにより、Poco F6も非常に多くのカスタムROMに対応しており、改造用途でも高い人気があります。
カスタムROM導入の最大のメリットはパフォーマンスの向上と不要なアプリの排除です。
MIUI標準ROMにはプリインストールアプリや広告が多く含まれていますが、AOSP系カスタムROM(Pixel ExperienceやLineageOSなど)ではシンプルなUIと軽快な動作を体感できます。
これによりバッテリー持ちや操作レスポンスの改善が期待できます。
また、Poco F6はグローバル市場を意識して作られているため、カスタムROMの種類が豊富なのも魅力です。
多くの開発者が積極的に対応しているため、アップデートや新機能の導入も早い傾向があります。
しかし一方で、注意点もあります。
Poco F6はRedmi K70(コードネーム:vermeer)に基づくため、間違ったモデル用のROMを選ぶと端末が起動しなくなることがあります。
また、カスタムROMの導入にはブートローダーアンロックやTWRPの導入といった手順が必要で、技術的な知識が不可欠です。
さらに、標準ROMでは動作していたFelicaやおサイフケータイ機能がカスタムROMでは動作しなくなることもあります。
特に日本仕様では独自のNFCモジュールを搭載しているケースがあり、これがカスタムROM側で対応されていないことが原因です。
このように、Poco F6へのカスタムROM導入は非常に高い自由度とメリットを提供しますが、リスクと手間も伴います。
導入を検討する際は、まず対象のROMとバージョンがPoco F6に対応していることを必ず確認し、自己責任で作業を進めることが重要です。
Redmi端末にカスタムromを導入する際のリスク
Redmi端末はカスタムROM導入の自由度が高く、多くのユーザーや開発者が改造に挑戦しています。
しかし、カスタムROMの導入はメーカー保証外の行為であり、いくつかのリスクが伴うことを理解しておく必要があります。
まず最も深刻なリスクは、端末の文鎮化(起動不能状態)です。
誤った手順や対応していないROMをインストールすると、端末が起動しなくなることがあります。
この場合、工場出荷状態に戻すためのEDL(Emergency Download Mode)作業や専用ツールが必要になり、復旧できない場合もあります。
次に、機能の一部が失われる可能性があります。
特に日本版Redmi端末はFeliCaやeSIMなど特有の機能を搭載しており、カスタムROM導入後にこれらが動作しなくなる事例が報告されています。
MagiskモジュールやLSPosedなどで対策できることもありますが、完全な互換性は保証されていません。
また、セキュリティとプライバシーのリスクも考慮する必要があります。
カスタムROMはオープンソースで開発されていますが、中には信頼性の低い非公式ROMも存在します。
個人情報の漏えいや不正アクセスのリスクを避けるためには、信頼できる開発元やフォーラムからのみROMをダウンロードすることが大切です。
さらに、メーカーやキャリアのサポートが受けられなくなる点にも注意が必要です。
ブートローダーのアンロックが確認されると公式保証が失効するため、修理や交換対応が有償になることがあります。
このように、Redmi端末へのカスタムROM導入は多くのメリットがある一方で、失敗時のリスクも大きい行為です。
事前に十分な情報収集を行い、バックアップを取り、安全な環境で自己責任で作業を行うことが成功の鍵となります。


