Redmi Padシリーズの購入を検討している方の中には、Redmi Padのグローバル版との違いが気になって検索している人も多いはずです。
日本版とグローバル版・中国版では、見た目は似ていても技適マークの有無やアップデート対応、日本語入力の可否などに違いがあります。
この記事では、xiaomi pad 6、Xiaomi Pad 5、Redmi Pad Pro、Redmi PAD SEなどの主要モデルを比較し、それぞれの注意点をわかりやすく解説します。
電子書籍に適したモデルの選び方も紹介していますので、用途に応じた最適な選択ができるようになります。
購入前に確認すべきポイントを整理して、安心して使えるタブレットを選びましょう。
Redmi Padのグローバル版との違いを解説
- Xiaomi Padのグローバル版と日本版の違いは何
- Xiaomi Pad 6のグローバル版と日本版の違い
- Xiaomi Pad 5のグローバル版と日本版の違い
- 中国版とグローバル版の違いは
- グローバルROMとGlobal Versionの違い
- Redmi PAD SEで日本語入力はできるのか
Xiaomi Padのグローバル版と日本版の違いは何

Xiaomi Padシリーズにおけるグローバル版と日本版の違いは、見た目や基本スペックではなく「ソフトウェア面の仕様」と「技適認証の有無」が主なポイントになります。
特に日本国内で安心して使用するには、技適マークの有無が重要な判断材料となります。
まず前提として、Xiaomiが販売するタブレットはグローバル市場向けに広く展開されており、日本国内ではその一部が正規代理店や家電量販店を通じて「日本版」として販売されています。
一方で、AliExpressなどを通じて入手可能な「グローバル版」は、外見上やハードウェアの仕様にほとんど違いはありません。
ディスプレイサイズ、CPU、メモリ容量、バッテリー容量などの基本的な構成は共通しているため、表面的にはほぼ同じ製品に見えることが多いです。
しかし、実際に使用する上ではいくつかの注意点があります。
まず一つ目は、アップデートやサポート体制の違いです。
日本版はXiaomi Japanが提供するMIUI(AndroidベースのOS)を搭載しており、定期的なシステムアップデートや不具合修正の対象になります。
これに対して、グローバル版の中にはショップ独自のROM(いわゆる「ショップROM」)が導入されたものもあり、これらは公式のアップデート対象外である場合があります。
つまり、新しいAndroidバージョンやセキュリティパッチを適用できない可能性があるということです。
次に技適マークの問題があります。
技適とは「技術基準適合証明」の略で、日本国内で電波を発する無線機器にはこのマークが必要です。
Wi-FiやBluetoothを搭載するタブレットも例外ではありません。
日本版のXiaomi Padには必ずこの技適マークが表示されていますが、グローバル版には技適表示がないか、もしくは不正な方法で表示されているケースもあります。
法律的には、技適を取得していない機器の電源を日本国内で入れるだけでも電波法違反になる可能性があります。
さらに、購入後のサポート体制にも差があります。
日本版であれば、初期不良や故障時には国内で修理対応を受けられることが多く、やり取りも日本語でスムーズです。
一方でグローバル版の場合、修理は中国のサポート窓口に直接依頼する必要があり、発送や手続きのハードルが高くなります。
これらの点を総合すると、見た目やスペックは同じでも、グローバル版には「自己責任で使うべき側面」が強いといえるでしょう。
コストを抑えたい場合には魅力的ですが、安全性やサポートを重視するのであれば、日本正規版を選ぶのが無難です。
Xiaomi Pad 6のグローバル版と日本版の違い
Xiaomi Pad 6におけるグローバル版と日本版の違いは、基本スペックではなく「対応バンド、アップデート環境、技適認証の有無」など、実用性に直結する部分にあります。
特に日本国内で安定的かつ法的に問題なく使いたい場合には、慎重な判断が求められます。
スペック面で言えば、グローバル版と日本版にほとんど差は見られません。
どちらもSnapdragon 870チップセット、11インチWQHD+ディスプレイ、144Hzのリフレッシュレートといった強力なハードウェアを備えています。
また、Dolby VisionやDolby Atmos対応のスピーカーシステムなど、エンタメ利用にも最適な仕様は共通しています。
つまり、使い勝手という点ではどちらを選んでも大きな違いはありません。
一方で、OSの更新可否や言語対応、アプリの互換性には差が出る場合があります。
日本版はMIUI for Padの正式サポート対象となっており、Google Playや日本語UI、日本向けの標準アプリなどがスムーズに使えます。
これに対し、グローバル版にはいくつかのパターンが存在し、正規のGlobal ROMが搭載されているものと、ショップ独自にROM焼きされた非公式バージョンが混在しています。
後者の場合はアップデートが配信されないことが多く、セキュリティ上の懸念も拭えません。
さらに、技適マークの有無も重要です。
グローバル版は基本的に海外市場向けであり、必ずしも日本の電波法に準拠しているとは限りません。
技適マークがなければ、Wi-FiやBluetoothの使用も法的に問題となります。
特に職場や教育現場での利用を検討している場合、技適の有無は見過ごせないポイントです。
最後に価格面ですが、グローバル版は海外通販サイトでの購入が主流となるため、日本版よりも安価に手に入るケースが多いです。
しかし、トラブル時のサポートが受けづらく、返品や修理も自己対応になる点は大きなリスクです。
このように、Xiaomi Pad 6はハード的には魅力的なモデルですが、グローバル版を選ぶ際はソフト面や法的制約を十分に理解した上で判断する必要があります。
Xiaomi Pad 5のグローバル版と日本版の違い

Xiaomi Pad 5に関しては、グローバル版と日本版の違いが明確に分かれるポイントが複数存在します。
特に注目すべきは、Googleサービスの正式対応状況、ファームウェアのアップデート可否、そして技適マークの有無です。
まず、グローバル版のXiaomi Pad 5は、Google Mobile Services(GMS)を標準搭載しており、Google PlayストアやYouTube、Gmailといったアプリも最初から利用できます。
これは中国国内向けのモデル(中国版)とは大きく異なる点で、中国版はGMS非搭載であるため、Google系のアプリを手動でインストールする必要があります。
グローバル版を選ぶことで、日本においてもGoogleサービスをスムーズに利用できるという利点があります。
一方で、日本版はグローバル版をベースに、国内の法律や通信規格に合わせて調整されたモデルです。
特に、技適マークが明記されており、日本国内での使用に法的な問題はありません。
また、Xiaomi Japanによる公式サポートの対象となるため、修理・交換・アップデートなどの対応がスムーズに行えます。
ただし、グローバル版でも技適マークが表示されているケースがありますが、これはROMの書き換えによる偽装表示である可能性も指摘されています。
見た目には「技適あり」に見えても、実際には総務省の認可を受けていないという例もあるため、注意が必要です。
また、アップデート面では、日本版はMIUIのグローバル安定版をベースとしているため、公式のアップデート通知が届きやすく、セキュリティ面でも安心です。
これに対して、AliExpressなどで販売されている一部のグローバル版は、ROMがカスタマイズされており、今後のアップデートが保証されていないことがあります。
仮にOSを自分で入れ替えたい場合には、ブートローダーのアンロックやROM焼きといった技術的な知識が求められます。
このように、Xiaomi Pad 5のグローバル版と日本版の違いは、価格や仕様だけでなく、使用環境や法的リスクに直結する部分にも及びます。
価格差だけを見て判断せず、自分の利用目的に応じて適切なバージョンを選ぶことが重要です。
中国版とグローバル版の違いは
中国版とグローバル版の違いは、単なる言語設定の差ではなく、使用環境や利便性、法的側面にも関わる重要なポイントです。
購入前にそれぞれの特徴を把握しておくことが、トラブルの回避や快適な使用につながります。
まず最も大きな違いは、搭載されているソフトウェアです。
中国版のXiaomi製品には「MIUI中国版」が搭載されており、Google関連サービス(Gmail、Google Playストア、YouTubeなど)はインストールされていません。
代わりにXiaomi独自のApp Storeや中国国内向けのアプリがプリインストールされています。
中国国内ではGoogleサービスが制限されているため、このような構成になっています。
一方、グローバル版には「MIUIグローバル版」が搭載されており、Googleサービスが標準で導入されています。
日本を含む多くの国ではGoogle関連アプリの利用が前提となっているため、グローバル版の方が利便性は高いと言えるでしょう。
次に、対応言語にも差があります。
中国版では中国語と英語が基本となり、それ以外の言語は設定できないことが多く、日本語にも対応していません。
これに対してグローバル版では多言語対応が基本で、日本語表示や入力にも完全に対応しているモデルがほとんどです。
また、アップデートやサポート体制も異なります。
中国版は中国国内向けに配信されるファームウェアが対象であり、アップデートの頻度や内容も中国市場のニーズに合わせられています。
グローバル版ではより広範囲なユーザーを対象としており、言語やアプリ互換性を含む調整が加えられているため、安定性や汎用性に優れています。
そして最も注意すべきは、技適マークの有無です。
日本国内で電波を発する製品を使用する場合、技適(技術基準適合証明)の表示が必要です。
中国版にはこのマークが無い場合が多く、日本で使うと電波法違反となる可能性があります。
一方、グローバル版であっても技適が付いていないケースがあるため、購入時には技適マークの有無を必ず確認する必要があります。
このように、中国版とグローバル版は外見上は似ていても、内部仕様や使用環境に大きな違いがあります。
価格の安さだけで中国版を選ぶと、後々使いにくさや法的リスクに直面することもあるため、慎重な判断が求められます。
グローバルROMとGlobal Versionの違い
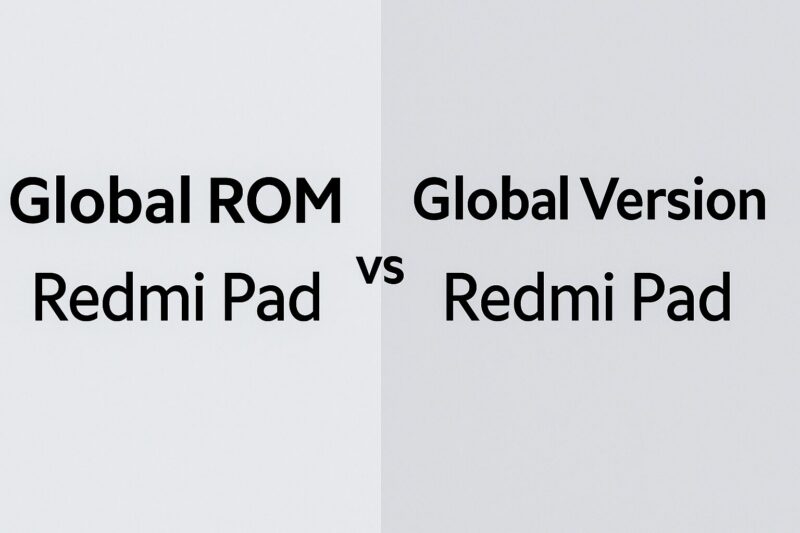
グローバルROMとGlobal Versionの違いは一見すると紛らわしいですが、両者には明確な差があります。
この違いを理解しておくことで、誤って不安定な端末を購入するリスクを避けることができます。
まず、Global Versionとは、メーカーであるXiaomiが公式に国際市場向けに製造・出荷しているモデルのことを指します。
このバージョンには、工場出荷時点で正式なグローバルファームウェアが導入されており、多言語対応、Googleサービスの標準搭載、そしてOTA(Over The Air)による自動アップデートの受信などがサポートされています。
さらに、技適マークが表示されていることも多く、日本国内での使用にも適していると言えるでしょう。
一方で、グローバルROMとは、本来は中国国内向けに作られた端末に、ショップや個人が独自にグローバルファームウェアをインストール(いわゆる「ROM焼き」)したものを指します。
この行為自体は違法ではありませんが、技術的な問題を含む可能性がある点に注意が必要です。
特に、アップデートが自動で受け取れないことや、Googleサービスが不安定に動作するケースも報告されています。
さらに、ROMの焼き方によっては、ブートローダーをアンロックした状態で出荷されていることもあり、セキュリティ的にリスクを抱える場合があります。
もう一点重要なのは、保証やサポートの違いです。
Global Versionであれば、販売地域によっては正規のサポートを受けることができますが、グローバルROMの場合は非公式扱いとなり、サポート対象外となることが一般的です。
また、ショップがROM焼きを行った端末には「技適マークを表示する非公式な手法」が用いられていることもあり、法的には問題がある可能性も否定できません。
つまり、Global Versionはメーカーが正式に提供する国際モデルであるのに対し、グローバルROMは第三者が手を加えた改造品という位置づけです。
価格が安く表示されていても、グローバルROM端末はその安さに見合ったリスクが潜んでいることを理解しておく必要があります。
Redmi PAD SEで日本語入力はできるのか
Redmi PAD SEでは、購入するバージョンによって日本語入力が可能かどうかが大きく異なります。
具体的には「正規グローバル版」であれば、設定メニューから簡単に日本語を選択でき、日本語入力にも完全対応しています。
この製品はXiaomiが海外向けに展開する廉価タブレットとして人気ですが、「グローバル版」とされている製品の中には、中国国内モデルにショップ独自のグローバルROMを焼いたものも存在しています。
こうしたROMは日本語表記が一部しか対応していない場合や、Google日本語入力が正常に動作しないこともあります。
また、OS自体に不安定さが見られる場合もあるため注意が必要です。
対して、正規のグローバル版(パッケージや製品説明に「Global Version」と記載されているもの)であれば、MIUI for Padのグローバルファームウェアが搭載されており、言語設定で日本語を選ぶことができます。
さらに、Gboard(Googleキーボード)やSimejiなどの日本語IMEも通常どおりインストール・利用できるため、入力面での不便さは感じにくいでしょう。
なお、初期設定時に表示言語として日本語を選べない場合は、ROMの種類が非公式のものである可能性があります。
このような端末では一部機能が制限されていたり、アップデートによって突然日本語が使えなくなることもありえます。
したがって、Redmi PAD SEで日本語入力を確実に使いたいのであれば、「Global ROM」ではなく「Global Version」と明記された製品を選ぶことが非常に重要です。
安価な価格に惹かれて購入してしまうと、後々設定変更やアプリ導入に手間取るだけでなく、サポートも受けにくくなる可能性があります。
日本語環境での安定した使用を前提にするなら、信頼できる正規販売ルートでの購入が安心です。
Redmi Padのグローバル版との違いによる注意点と選び方
- Redmi Pad Proにおける注意点とは
- 技適マークの有無と電波法のリスク
- アップデートの可否とROMの種類
- グローバル版で使えないアプリはある?
- 電子書籍用途での最適モデルは?
- 購入前に確認すべき販売表記の違い
Redmi Pad Proにおける注意点とは
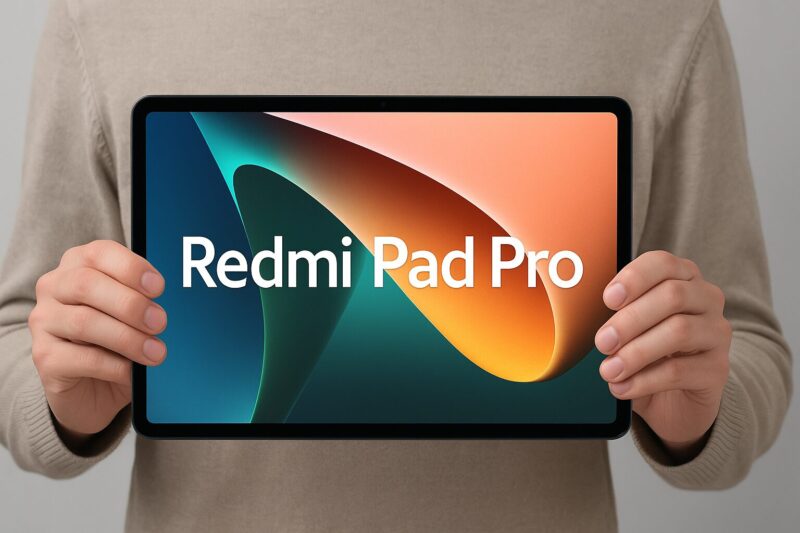
Redmi Pad Proを検討している際には、価格や性能の魅力だけでなく、いくつかの注意点を事前に理解しておく必要があります。
とくにAliExpressなどで販売されているモデルの多くが「中国版にグローバルROMを焼いた仕様」であることが多く、これが様々なトラブルの原因となることがあります。
最初に確認すべきは、その製品が「Global Version」か「Global ROM」かです。
前者はXiaomiが公式に海外向けとして出荷している製品で、Googleサービス、マルチ言語対応、正規アップデートなどが利用可能です。
一方、後者は中国国内モデルに非公式のグローバルOSが導入されたもので、アップデートが受け取れない、アプリが一部動かないなどの問題を抱えているケースがあります。
これが、購入後に「思っていた通りに動かない」といった不満につながる大きな要因の一つです。
また、ブートローダーの状態にも注意が必要です。
多くのROM焼きモデルでは、ブートローダーが再ロックされた状態で販売されていますが、この処理に失敗していると、将来的なアップデートやROMの再インストール時に文鎮化(起動不可)するリスクが高まります。
初心者の方が手を加えるのはハードルが高く、設定に自信がない方は避けたほうが無難です。
さらに、Redmi Pad Proは国内販売が少ないため、万が一不具合が発生した場合のサポート体制も限定的です。
日本のXiaomi公式サポートでは修理受付を断られる可能性があり、海外のサポート窓口と英語でやり取りを行い、かつ修理品を国際配送する必要があります。
これは時間的にも費用的にも大きな負担となるため、購入時には保証対応の有無を確認しておくことが大切です。
加えて、Redmi Pad Proのような中国市場向け端末では、技適マークがない可能性が高く、後述のように日本での使用には法的な問題が生じることがあります。
この点も見逃せない注意点です。
Redmi Pad Proは非常にコストパフォーマンスの高いタブレットですが、こうした注意点を理解せずに購入すると、後悔につながるケースもあります。
性能と価格だけで判断せず、利用環境やサポート面まで含めて慎重に選びましょう。
技適マークの有無と電波法のリスク
日本国内でWi-FiやBluetoothを使う電子機器を合法的に利用するためには、「技適マーク」の存在が欠かせません。
技適とは、正式には「技術基準適合証明」と呼ばれる制度で、総務省が定める無線設備の技術基準に適合していることを示す証です。
このマークが端末に付いていない場合、たとえ個人の使用であっても、日本の電波法に違反する可能性があります。
たとえば、海外から輸入したXiaomiのタブレット、特に中国版やグローバルROM焼きの製品には、技適マークが付いていないか、偽装された表示がされている場合があります。
一見表示されているように見えても、正式に日本の認可を受けていない可能性があるため注意が必要です。
電波法では、技適を取得していない無線機器で電波を発する行為、すなわち電源を入れてWi-FiやBluetoothを使用すること自体が違法とされています。
この違反が発覚した場合、最悪の場合「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
実際には即時逮捕といった極端なケースは稀ですが、法的にはそのような重い罰則が設けられているのです。
さらに、技適がない機器を使用することで、周囲の無線通信に干渉を引き起こすリスクもあります。
とくに職場や学校、公共施設などで無断で技適なし端末を使ってしまうと、知らず知らずのうちに他人の通信を妨害してしまう恐れがあるのです。
とはいえ、「どうしても海外製品を使いたい」という人向けに、総務省では「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」を設けています。
これは、申請により180日間限定で技適のない機器を合法的に使える制度です。
ただしこの制度も「個人の実験目的」に限られており、日常使用を前提にしたものではありません。
こう考えると、海外版タブレットを購入する際には、コスト面だけでなく技適の有無を最重要視するべきです。
安全・安心に日本国内で利用したいのであれば、正規の日本向け製品を選ぶことが最も現実的な選択肢といえるでしょう。
アップデートの可否とROMの種類

Xiaomiタブレットを購入する際、もう一つ重要なチェックポイントとなるのが「アップデートの可否」と、それに関わる「ROMの種類」です。
これを見落とすと、セキュリティ面や機能性の面で不便を感じることになる可能性があります。
Xiaomi製品に搭載されているOSはMIUIと呼ばれる独自UIで、基本的にはAndroidをベースにしています。
しかし、このMIUIには「中国版」「グローバル版」「ショップROM(カスタムROM)」といった複数のバリエーションが存在します。
とくに問題となりやすいのは、「中国版の端末にショップが独自にROMを焼いたグローバルROM端末」です。
このようなショップROMは、公式のアップデートが配信されない場合が多く、セキュリティパッチも滞ることがあります。
仮にGoogleサービスが使えるように見えても、それはショップが独自に構成した非公式のOSであることが多く、将来的にアプリの互換性やOSの挙動に不具合が出るリスクがあります。
OTAアップデート(自動アップデート)が届かないこともよくあるため、システムを常に最新に保ちたいユーザーには向いていません。
一方、正式な「Global Version」に搭載されているROMは、Xiaomi公式のグローバルファームウェアであり、定期的なアップデート配信が保証されています。
新機能の追加や不具合修正が適用されやすく、安定して長く使えるという点で安心感があります。
また、ROMの種類は端末の安全性にも影響します。
ブートローダーがアンロックされた状態で出荷されるカスタムROM機は、悪意あるアプリやマルウェアの侵入リスクが高くなることがあります。
知らずに購入すると、セキュリティ面で重大なトラブルに発展する可能性もあるため注意が必要です。
このように、見た目やスペックだけではわからないROMの種類とアップデート体制は、製品選びの成否を大きく左右する要素です。
信頼できる販売元でGlobal Versionの表記が明記された製品を選ぶことで、長期的に安定して利用できるタブレットを手に入れることができます。
価格だけでなく、アップデートの継続性も含めて総合的に判断することが大切です。
グローバル版で使えないアプリはある?
グローバル版のXiaomiタブレットは、基本的にGoogleサービスが利用できる仕様になっており、多くのアプリが問題なく動作します。
ただし、どのグローバル版でも完全に同じ環境で使えるとは限らず、「ショップROM」などの非公式なファームウェアが使われている端末では一部のアプリに不具合が出ることがあります。
特に影響を受けやすいのが、日本国内向けに最適化されたアプリです。
例えば、モバイルSuicaや一部の銀行系アプリ、または著作権管理が厳しい動画配信サービス(Netflix、Amazonプライム・ビデオなど)などでは、動作に必要なセキュリティ条件が満たされていない場合があります。
このようなアプリは、端末が「安全である」と認識できないとインストールや起動自体がブロックされる仕組みになっているため、グローバルROM端末では正常に使えないケースもあります。
また、Widevineのセキュリティレベルによっても利用状況が変わります。
Widevine L1に対応していない端末では、NetflixやAmazonプライムでHD画質が再生できず、SD画質に制限されることがあります。
たとえグローバル版であっても、L1に非対応なモデルやROMの改造が原因でL3と認識されてしまうケースも報告されています。
一部のゲームアプリでも注意が必要です。
改造されたOSを検知したアプリが起動時にエラーを出すことがあり、これは「root化やROM焼きされた端末はセキュリティ的に信用できない」と判断されているためです。
具体的には『ポケモンGO』や『原神』などの一部人気タイトルで、このような事象が確認されています。
このように、グローバル版だからといって必ず全てのアプリが使えるとは限りません。
とくに非公式ROMが関係している場合、事前に「そのROMはGoogle Playの認証を受けているか」「セキュリティチェックを通過しているか」などを確認するのが望ましいです。
アプリの互換性に不安がある場合は、公式のGlobal Versionを選ぶことが最も安心できる選択となるでしょう。
電子書籍用途での最適モデルは?
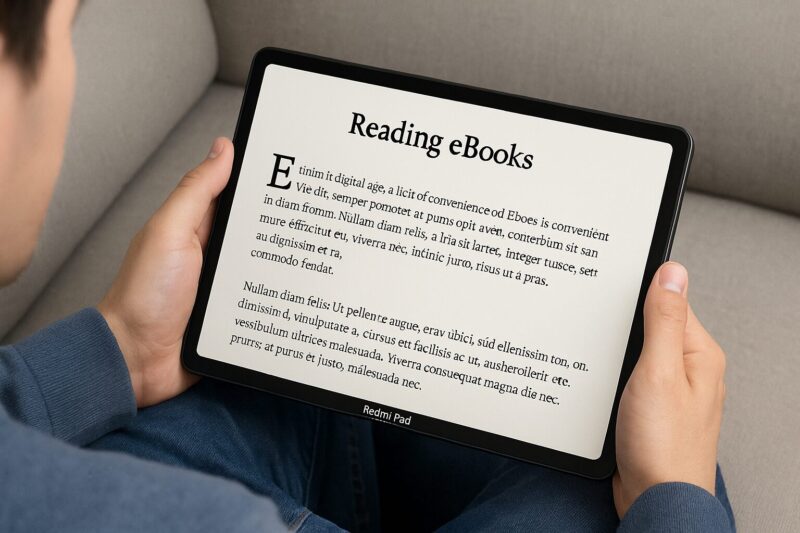
電子書籍を読む目的でタブレットを選ぶ場合、スペックの高さよりも「表示の快適さ」と「持ち運びやすさ」に注目するのがポイントです。
その観点から見ると、XiaomiのRedmi Padシリーズ、とくにRedmi Pad SEやRedmi Pad 6GBモデルは非常にバランスが取れた選択肢となります。
まず画面サイズですが、10〜11インチクラスのディスプレイは雑誌や漫画を見開き表示で読むのに適しています。
Redmi Pad SEは11インチのフルHD+ディスプレイを採用しており、文字や図版もはっきりと見える解像度です。
さらに、90Hzのリフレッシュレートに対応しているため、ページ送りやスクロール時の動作がなめらかで目の負担も少なくなります。
もうひとつの重要な要素が重量です。
電子書籍は長時間手に持って読むことが多いため、重すぎる端末では疲れやすくなります。
Redmi Pad SEの本体重量は約478gと比較的軽量で、手持ちでも苦にならないレベルです。
また、バッテリー容量も8000mAhと大きく、頻繁に充電する必要がないのもメリットになります。
加えて、電子書籍の形式やアプリとの相性も見逃せません。
日本の電子書籍サービスでは「Kindle」「楽天Kobo」「BookLive!」「コミックシーモア」などが人気ですが、どれもAndroid端末向けに公式アプリを提供しています。
グローバル版であってもGoogle Playが利用できるモデルであれば、これらのアプリは問題なく使用できます。
一方で、注意すべきなのは「中国版」や「非公式グローバルROM」を搭載した端末です。
Google Playが最初からインストールされていない可能性があり、場合によってはアプリが動作しなかったり、インストールできなかったりすることもあります。
電子書籍目的であっても、安さだけで選んだ結果、目的のアプリが使えないという本末転倒な状況になる恐れがあります。
このように、電子書籍用途では高スペックなゲーミングモデルよりも、軽量で高解像度かつ安定した環境が整っているグローバル版のRedmi Pad SEやRedmi Pad 6GBモデルが最適と言えるでしょう。
購入時は、Googleサービスに正式対応しているかどうかをしっかり確認しておくことが快適な読書体験への第一歩です。
購入前に確認すべき販売表記の違い
Xiaomiタブレットを購入する際に、多くの人が見落としがちなのが「販売表記の違い」です。
これらは一見すると似たような言葉に見えますが、実際には製品の正規性や機能性に大きく関わる重要な情報です。
特に「Global Version」「Global ROM」「China Version」などの表記は、購入前に必ず確認すべきポイントです。
最も信頼できるのは「Global Version(グローバルバージョン)」という表記です。
これはXiaomiが正式に海外市場向けに製造・販売しているモデルを指し、Googleサービスが標準搭載されているほか、アップデートの配信、マルチ言語対応、日本語設定も含まれています。
また、技適マークが表示されていることも多く、日本での使用にも安心感があります。
一方で、注意が必要なのが「Global ROM(グローバルROM)」という表記です。
これは、中国版の端末にショップなどが独自にグローバル用のROMをインストールした製品を意味します。
見た目にはグローバル版と似ていますが、ROMが非公式である場合、アップデートが届かない、Googleサービスが不安定に動作する、技適が偽装されているといったリスクがあります。
また、「China Version」や「CN Version」という表記は、中国国内向けの純正モデルであることを示しています。
こちらはGoogleサービスが初期状態で搭載されておらず、ROM焼きなどの作業を行わない限り、Google Playなどのアプリが使用できません。
加えて、日本語への対応も限定的で、設定やメニューの多くが中国語または英語表記になることがあります。
こうした販売表記の違いは、購入時の製品ページや商品説明欄に小さく書かれていることが多いため、見落とさないよう注意が必要です。
また、購入先が信頼できる販売店であるかどうかも非常に重要です。
価格が安いからといって、記載のないグローバルROM端末を選んでしまうと、結果的に不具合や法的リスクを抱えることになりかねません。
このように、Xiaomiタブレットを購入する際は、スペック表だけでなく「Global Version」と明記されているか、「技適対応」と書かれているかをチェックすることで、後悔のない選択ができるようになります。
表示されている単語一つひとつが、安心して使えるかどうかの分かれ道になるのです。


