Xiaomiから待望の新型スマートフォン、Xiaomi 15Tのグローバル版が発表されました。
その詳細なスペック、特に注目されるライカ共同開発カメラや大画面のAMOLEDディスプレイ搭載といった特徴に関心が集まっています。
また、上位モデルであるXiaomi 15T Proとの違いや、それぞれの価格、そして最も気になる日本発売日はいつになるのか、多くのファンが情報を待っています。
さらに、前モデルとなったXiaomi 14Tとの比較を通じて、その進化点も気になるところです。
この記事では、大容量バッテリーと急速受電性能も含め、Xiaomi 15Tの全貌を徹底的に解説します。
Xiaomi 15Tのスペックと主な特徴
- グローバル版の発表内容を速報
- Dimensity 8400-Ultra搭載スペック
- 120Hz対応AMOLEDディスプレイ搭載
- ライカ共同開発カメラの実力
- 5500mAhバッテリーと急速受電
グローバル版の発表内容を速報

Xiaomiは、2025年9月24日(現地時間)に新製品発表会を開催し、新型スマートフォン「Xiaomi 15T」を正式にグローバル発表しました。
この発表会では同時に、上位モデルである「Xiaomi 15T Pro」も披露されており、毎年多くの注目を集めるTシリーズが新たなラインナップで登場した形です。
このTシリーズは、Xiaomiの最上位フラグシップ(Xiaomi 15シリーズなど)で培われた最先端の技術やプレミアムな特徴を一部受け継ぎつつ、より多くのユーザーが手に取りやすい価格帯を実現した「準フラグシップ」として確固たる地位を築いています。
つまり、性能と価格のバランスを極限まで追求した、非常にコストパフォーマンスに優れたシリーズと言えるでしょう。
前モデルのXiaomi 14Tシリーズも日本国内で正式に発売され、特にキャリアのキャンペーンと相まって大きな話題となりました。
そのため、その後継機である今回のXiaomi 15Tにも、日本市場での大きな成功が期待されています。
日本での正式発表は目前に迫る9月26日に予定されています。
そこで価格や発売日、そして国内での取り扱いキャリアなどの詳細が明らかになる見込みです。
まずはグローバル版の発表内容から、その驚くべき性能を詳しく見ていきましょう。
Dimensity 8400-Ultra搭載スペック
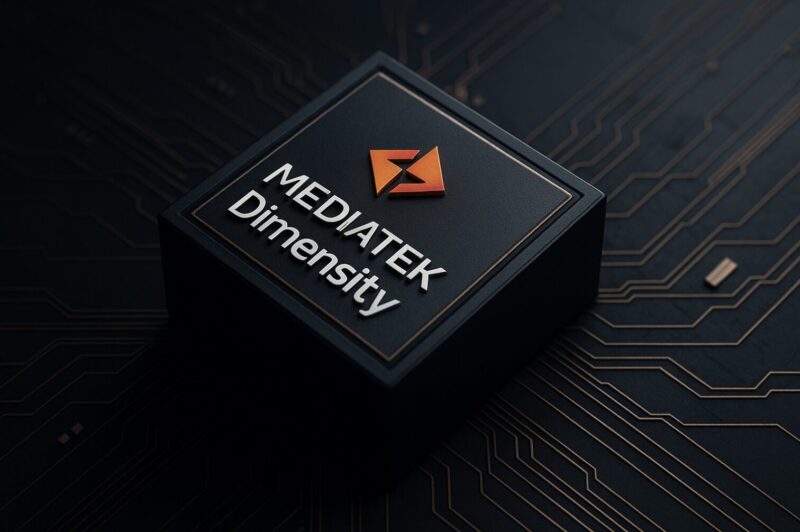
Xiaomi 15Tのパフォーマンスを司る心臓部、SoC(System on a Chip)には、MediaTek製の最新チップ「Dimensity 8400-Ultra」が採用されています。
これは、ミドルハイから準ハイエンドクラスのスマートフォン向けに設計されており、日常的なウェブ閲覧やSNS、動画視聴はもちろん、グラフィックス負荷の高い多くの3Dゲームにも対応できる、非常に快適な処理性能を備えています。
このチップは、同じくXiaomi傘下のブランドから発売され人気を博した「POCO X7 Pro」にも搭載されており、その安定したパフォーマンスの高さはすでに多くのユーザーによって証明済みです。
AnTuTuベンチマークスコア(v10)では、150万点前後に達する性能が期待でき、同価格帯のスマートフォンの中でも頭一つ抜けた処理能力を誇ります。
さらに、その高いパフォーマンスを支えるメモリとストレージにも妥協はありません。
高速メモリとストレージの仕様
RAM(メモリ)は12GB(LPDDR5X)、ROM(内部ストレージ)は256GBまたは512GB(UFS4.1)という構成です。
LPDDR5XとUFS4.1は、それぞれ現行のスマートフォンにおいてトップクラスの高速規格です。
これにより、アプリの起動や複数アプリ間の切り替え、データの読み書きが非常にスムーズに行われます。
チップセットの性能を最大限に引き出し、ユーザーの体感速度を向上させる重要な要素となっています。(参照:MediaTek Dimensity 8000シリーズ公式サイト)
このように、Xiaomi 15Tはライトな使い方から少しヘビーなゲームプレイまで、幅広いニーズに応えることができる、非常にバランスの取れた高いパフォーマンスを実現しています。
120Hz対応AMOLEDディスプレイ搭載
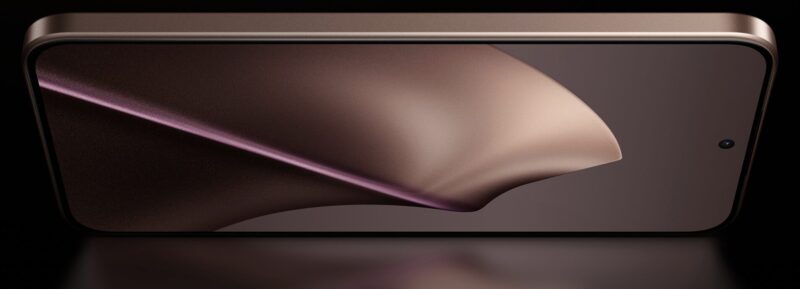
スマートフォン体験の質を大きく左右するディスプレイには、6.83インチの有機EL(AMOLED)ディスプレイを搭載しています。
解像度はFHD+よりも精細な1.5K(2772×1280)となっており、テキストや画像をシャープに表示します。
AMOLEDは、液晶とは異なり画素自体が発光するため、引き締まった黒の表現や高いコントラスト比が特徴です。
これにより、映画などの映像コンテンツをより臨場感豊かに楽しめます。
前モデルの6.67インチから一回りサイズアップし、さらにベゼル(画面の額縁部分)の幅を1.5mmまで極限まで狭めたことで、画面占有率が向上し、より高い没入感を得られるようになりました。
リフレッシュレートは最大120Hzに対応しており、ウェブサイトのスクロールやSNSのタイムライン表示、対応ゲームのプレイが驚くほど滑らかです。
また、ピーク輝度は公称3200nitsと非常に明るく、真夏の日中の屋外など、強い直射日光下でも画面の表示内容をはっきりと認識できる高い視認性を確保しています。
生体認証については、利便性の高い画面内指紋認証センサーを搭載。画面に指を置くだけで素早くロックを解除できます。
また、スピーカーはデュアルステレオ構成で、立体音響技術のDolby Atmosにも対応しているため、映像コンテンツを迫力のあるサウンドで楽しむことが可能です。
ライカ共同開発カメラの実力

Xiaomi 15Tの最大の魅力の一つが、ドイツの名門カメラメーカー「Leica(ライカ)」との共同開発によるトリプルカメラシステムです。
スマートフォンのカメラでありながら、ライカ独自の哲学に基づいた画質チューニングが施されており、深みのある写真撮影が楽しめます。
カメラのハードウェア構成は、以下の3つのカメラで構成されています。
| カメラ種別 | 画素数 | 仕様詳細 |
|---|---|---|
| メイン(広角) | 5000万画素 | F値1.7, 光学式手ブレ補正(OIS), Light Hunter 800センサー |
| 超広角 | 1200万画素 | 画角15mm相当, F値2.2 |
| 望遠 | 5000万画素 | 光学2倍ズーム相当, F値1.9 |
メインカメラには、優れたダイナミックレンジと集光性能を誇る「Light Hunter 800」センサーが採用されています。
これに光学式手ブレ補正(OIS)が組み合わさることで、夜景や薄暗い室内といった光量が不足する場面でも、ノイズや手ブレを抑えた明るくクリアな写真を撮影できます。
また、ソフトウェア面では、ライカらしい2つの色彩モード「Leica Authentic Look(オーセンティック)」と「Leica Vibrant Look(バイブラント)」を選択可能。
被写体や好みに合わせて、自然で深みのある色合いと、鮮やかで印象的な色合いを切り替えることができます。(参照:LeicaとXiaomiのパートナーシップについて)
Proモデルとのカメラ性能の違い
上位モデルであるXiaomi 15T Proも同じくライカ監修カメラを搭載していますが、望遠カメラの性能に明確な差が設けられています。
Xiaomi 15Tが使いやすい画角の光学2倍望遠であるのに対し、Proモデルは光学5倍のペリスコープレンズを搭載しています。
これにより、Proモデルは遠くの被写体を画質劣化なく、より大きく写し撮る能力に優れています。
5500mAhバッテリーと急速受電

近年のスマートフォン選びで最も重視される要素の一つであるバッテリーにおいて、Xiaomi 15Tは5500mAhという非常に大容量のバッテリーを搭載しています。
これは前モデルの5000mAhから10%も増量されており、一般的な使い方であれば、1日の終わりでもバッテリー残量を気にすることなく安心して使用できるスタミナが期待できます。
充電性能も抜かりはなく、67WのXiaomi HyperCharge(有線急速充電)に対応。
対応充電器を使用すれば、わずかな時間でバッテリー残量を大幅に回復させることが可能です。
朝の忙しい時間帯や、外出前の短い時間でも十分な充電量を確保できます。
ただし、注意点としてワイヤレス充電には対応していません。
この機能を日常的に利用しているユーザーは、上位モデルの15T Proを検討する必要があります。
これだけの大容量バッテリーを搭載しながら、本体の厚さは7.5mm、重量は194gと薄型軽量ボディを実現している点は特筆すべきです。
また、IP68等級の防水防塵性能を備えているため、突然の雨やキッチンなどの水回りでの使用も安心です。
IP68等級とは?
IP68の「6」は防塵性能が最高レベルであることを示し、粉塵の侵入を完全に防ぎます。
「8」は防水性能が最高レベルであることを示し、継続的に水中に沈めても内部に浸水しないことを意味します。
これにより、日常生活における多くの水濡れリスクから端末を保護します。(出典:総務省「国民のための情報セキュリティサイト」)
Xiaomi 15Tの価格と日本発売情報
- Xiaomi 15Tの価格はいくら?
- 上位モデルXiaomi 15T Proも登場
- Xiaomi 15T Proの価格をチェック
- 日本発売日はいつになるのか
- Xiaomi 14Tとの比較ポイント
- まとめ:Xiaomi 15Tは買いか?
Xiaomi 15Tの価格はいくら?

グローバル発表会で明らかにされた情報によると、Xiaomi 15Tの価格は649ユーロからに設定されています。
これを2025年9月現在の為替レートで日本円に単純換算すると、約11万3000円となります。
最も注目すべきは、この価格が前モデルであるXiaomi 14Tの発表時価格(649ユーロ)から据え置かれている点です。
ディスプレイの大型化やSoCの性能向上、バッテリー容量の増加といった複数のアップグレードを実現しながら価格を維持したことは、昨今の物価上昇や円安の状況を考えると、Xiaomiの驚異的な企業努力の表れと言えるでしょう。
日本での販売価格に関する注意点
前述の通り、この価格はあくまでヨーロッパ市場での価格です。
製品が日本で正式に発売される際には、輸入に関わる各種コストや国内での認証費用、為替レートの変動、そして販売戦略に応じたマーケティング費用などが価格に上乗せされます。
そのため、グローバル版の価格よりも数万円程度高くなるのが通例です。
Xiaomi 14Tの国内価格を参考にすると、13万円前後からのスタートとなる可能性も視野に入れておく必要があるかもしれません。
上位モデルXiaomi 15T Proも登場

Xiaomi 15Tと同時に、さらに高性能な上位モデル「Xiaomi 15T Pro」も発表されました。
基本的なデザインコンセプトやディスプレイサイズはXiaomi 15Tと共通ですが、より高い性能を求めるユーザーのために、主に以下の点で明確なスペックアップが図られています。
Xiaomi 15T Proの主な強化点
- SoC (プロセッサ): より高性能な「Dimensity 9400+」を搭載。最上位の処理性能を求めるゲームユーザーやプロフェッショナルな用途に応えます。
- 望遠カメラ: 光学5倍のペリスコープレンズを搭載。遠くの被写体を、画質をほとんど劣化させることなく鮮明に撮影可能です。
- 急速充電: 90Wの有線充電に対応し、充電時間をさらに短縮。加えて、手軽な50Wワイヤレス充電にも対応しています。
これらの違いから、最高のパフォーマンスやカメラのズーム性能、そしてワイヤレス充電の利便性を重視するユーザーにとっては、Xiaomi 15T Proが最適な選択肢となるでしょう。
Xiaomi 15T Proの価格をチェック

よりパワフルな上位モデルであるXiaomi 15T Proの価格は、799ユーロからと発表されています。これを日本円に換算すると約14万円となります。
こちらも無印モデルと同様に、驚くべきことに前モデルのXiaomi 14T Proから価格が据え置かれています。
特に光学5倍望遠カメラというハードウェア的にコストのかかるアップグレードを実現しながら価格を維持したことで、ハイエンドスマートフォン市場におけるコストパフォーマンスはさらに際立つものになりました。
無印モデルとの価格差は150ユーロ(約2万7000円)ですね。
この価格差で、SoCのアップグレード、光学5倍望遠、そしてワイヤレス充電が手に入ると考えると、Proモデルは非常に魅力的な選択肢に思えます。
日本発売日はいつになるのか

Xiaomi Japanは、公式X(旧Twitter)アカウントなどを通じて、2025年9月26日に日本市場向けの新製品発表会を予定していることを告知しています。
この場で、Xiaomi 15Tおよび15T Proの日本導入が正式に発表されることが確実視されています。
ただし、注意したいのは、これが「発表日」であり、必ずしも「発売日」とイコールではないという点です。
過去のTシリーズの国内発売スケジュールを振り返ると、正式発表から実際の発売までには数週間から1ヶ月程度の期間が設けられる傾向があります。
これまでのパターンから総合的に予測すると、日本での実際の発売日は2025年11月下旬から、年末商戦が本格化する12月初旬頃になる可能性が最も高いと考えられます。
販売チャネルについては、前モデルの実績から、Xiaomi公式サイトやAmazon、大手家電量販店でのSIMフリーモデルの販売が中心となるでしょう。
それに加え、auやUQ mobileといった一部キャリアでの取り扱いも継続して期待されます。
Xiaomi 14Tとの比較ポイント

Xiaomi 15Tが前モデルのXiaomi 14Tから具体的にどのように進化したのか、購入を検討する上で最も重要な比較ポイントです。
主要なスペックを比較表にまとめましたので、その違いを詳しく見ていきましょう。
| 項目 | Xiaomi 15T (新モデル) | Xiaomi 14T (前モデル) |
|---|---|---|
| ディスプレイ | 6.83インチ AMOLED (120Hz) | 6.67インチ AMOLED (144Hz) |
| SoC | Dimensity 8400-Ultra | Dimensity 8300-Ultra |
| バッテリー | 5500mAh | 5000mAh |
| 有線充電 | 67W | 67W |
| 本体サイズ (厚さ) | 7.5mm (薄型化) | 7.8mm / 7.95mm |
| 本体重量 | 194g | 193g / 195g |
| グローバル価格 | 649ユーロ~ | 649ユーロ~ |
この比較から分かる主な進化点は、「SoCの性能向上」「ディスプレイの大型化」「バッテリー容量の大幅な増加」という、スマートフォンの基本性能を底上げする重要な3点です。
特にバッテリー容量が10%も増えている点は、実際の利用シーンでの安心感に大きく貢献するでしょう。
一方で、リフレッシュレートが最大144Hzから120Hzに変更されている点には注意が必要です。
多くのユーザーにとって体感できるほどの差は少ないと考えられますが、スペック上の数値を重視する方にとっては気になる変更点かもしれません。
これは、バッテリー持続時間とのバランスを考慮した上での判断である可能性が考えられます。



